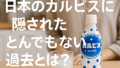ブログ村のランキングに参加中です!応援クリックで励まされます。
この記事を書いた人:健さん
元プロアスリート / 納棺師 / 介護福祉士
「人生健康第一」を伝えるブログメディア運営
最近、検診で脂肪肝を指摘されて「このまま放置して大丈夫なのか」「肝臓の脂肪をどうやって落とせばいいのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。私は元プロアスリートとして体と向き合い、納棺師として人の命の終わりを見届け、現在は介護福祉士として日常の健康と生活を支える現場にいます。そんな経験から辿り着いた信念があります。それは人生健康第一です。この記事では、肝臓の脂肪を落とす方法について、基本的なメカニズムから日常で実践しやすい改善ポイントまでを整理してお伝えします。検診でAST・ALT・γ-GTPの数値が高めと言われて気になっている方や、内臓脂肪やメタボを指摘されて生活を変えたいと考えている方にとっても、具体的なイメージを持ちながら一歩を踏み出すためのガイドになることを目指しています。
この記事のポイント
- 脂肪肝の基礎知識と肝臓の役割を理解できる
- 脂肪肝を放置した場合に起こりやすいリスクを理解できる
- 肝臓の脂肪を落とすための体重管理と運動のポイントを理解できる
- 飲み物や食品選びで肝臓をいたわる考え方を理解できる
肝臓の脂肪を落とす方法の基本理解
- 脂肪肝の基礎知識と種類
- 脂肪蓄積が進むメカニズム
- 放置で起こりやすい健康リスク
- 検査で確認できる主な指標
脂肪肝の基礎知識と種類
肝臓は、脂肪や糖、たんぱく質の代謝、毒素の解毒、胆汁の生成など、数百ともいわれる働きを担っている重要な臓器とされています。その肝臓に中性脂肪が多くたまった状態が、いわゆる脂肪肝と呼ばれる状態です。一般的には、肝臓を構成する肝細胞のうち一定以上の割合(およそ5〜10%程度)が脂肪化していると脂肪肝とみなされ、日本国内でも潜在的な脂肪肝の人が数千万規模にのぼると推計されています。 肝臓は沈黙の臓器といわれ、自覚症状がほとんどないまま変化が進むことも多いため、「数値が少し高いだけだから」と放置せず、状態を正しく理解することが大切です。
脂肪肝は大きく「アルコール性脂肪肝」と「非アルコール性脂肪肝(NAFLD)」に分けられるといわれています。さらに非アルコール性脂肪肝の中でも、単に脂肪がたまっているだけの段階をNAFL、その中に炎症や線維化が進んでいる状態をNASH(非アルコール性脂肪肝炎)と呼ぶ分類が一般的です。近年は、NAFLDやNASHという名称が、患者さんへの偏見やスティグマにつながりやすいとの議論から、代謝異常に着目した「MASLD」「MASH」という新しい病名も使われ始めています。アルコールをあまり飲まない方でも、糖質やカロリーのとり過ぎ、運動不足などの生活習慣によって脂肪肝になることがある点は、知っておきたいポイントです。[出典:肝炎情報センター代謝機能障害関連脂肪性肝疾患 | 肝炎情報センター]
脂肪蓄積が進むメカニズム
肝臓に脂肪がたまる背景には、エネルギーのとり過ぎと消費不足のバランスが大きく関わっていると考えられています。糖質や脂質を多く含む食事が続くと、使い切れなかったエネルギーは中性脂肪として蓄えられます。その一部が肝細胞の中にも蓄積し、少しずつ脂肪肝へ近づいていくと説明されることが多いです。本来、肝臓は余分な糖をグリコーゲンとして蓄えたり、脂肪酸をエネルギーとして利用したりしながら、体内のバランスを保っていますが、その処理能力を超える状態が続くと、肝臓自身が「脂肪をため込む倉庫」のような状態になってしまいます。
とくに、果糖ブドウ糖液糖などの果糖系甘味料は、血糖値を急上昇させにくい一方で、肝臓でまとめて代謝されるといわれています。その過程で中性脂肪や尿酸が増えやすく、肝臓への負担が大きくなる可能性が指摘されています。果物に含まれる自然な果糖は、食物繊維やビタミンと一緒にとることで吸収が緩やかになりやすいとされていますが、清涼飲料水やスイーツから液体・砂糖の形で大量にとると、処理が追いつかなくなりやすい点には注意が必要です。また、インスリンの効きが悪くなるインスリン抵抗性も、肝臓への脂肪蓄積を助長しやすいと考えられており、内臓脂肪の増加や運動不足、睡眠不足などさまざまな要因が複合的に関わっているとされています。
放置で起こりやすい健康リスク
脂肪肝は、初期の段階ではほとんど症状がなく、日常生活で自覚しにくいといわれています。しかし、放置して脂肪の蓄積や炎症が進むと、肝臓そのものだけでなく全身の代謝バランスにも影響が出やすくなると考えられています。一般的には、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病との関連が指摘されており、メタボリックシンドロームの一部として扱われることもあります。脂肪肝がある人は、インスリン抵抗性が強くなりやすく、血糖や中性脂肪が高めになりやすい傾向があるとされています。
さらに、NASHに進行した場合には、数年から十数年のスパンで肝硬変や肝がんに至るリスクが高まるとされています。炎症と線維化が進んだ肝臓は、元の状態に戻りにくくなると考えられており、早期の段階で生活習慣を整えることがとても重要です。症状がないからといって安心するのではなく、定期的な健康診断や血液検査で状態を把握し、早めに生活習慣を見直すことが重要と考えられます。とくに気になる症状がある方や、すでに他の病気で治療中の方は、自己判断を避けて医療機関や専門家に相談することが推奨されます。「なんとなくだるい」「疲れやすい」といったサインも、他の病気と重なっている場合があるため、一度チェックしておくと安心です。
検査で確認できる主な指標
脂肪肝の有無を推測するうえで、まず行われることが多いのが血液検査です。一般的には、AST、ALT、γ-GTPといった肝機能の数値がチェックされます。ALTが高めで、ASTとともに基準値を超えている場合、脂肪肝や肝炎など肝臓の炎症が疑われることがあります。数値が正常範囲にあっても、体質や他の病気との兼ね合いで評価が変わることもあるため、結果を見たときには単なる「高い・低い」だけで判断せず、必ず医師に解釈を確認することが大切です。
γ-GTPが高い場合は、アルコールの影響だけでなく、薬剤や脂肪肝などさまざまな要因が関係しているといわれています。血液検査に加えて、腹部エコー検査で肝臓の状態を直接確認することも一般的です。エコーでは、肝臓が白っぽく見える「bright liver」と呼ばれる所見が脂肪肝の目安として使われることがあります。また、必要に応じてCT検査やMRI検査、専門施設では肝臓の硬さを測るエラストグラフィーなどが検討されることもあります。これらの検査結果は、体調や他の病気との関係によって解釈が変わることがあるため、気になる結果が出た際には、早めに医師や専門家の説明を受けることが大切です。
肝臓の脂肪を落とす方法の実践ポイント
- 体重5%減が効果的とされる理由
- 運動で脂肪が減りやすい背景
- 果糖系甘味料を控える重要性
- 脂質の質を見直す考え方
- コーヒーと緑茶の活用ポイント
- 肝臓に良い食品の上手な取り入れ方
体重5%減が効果的とされる理由

脂肪肝の改善には、体重を大きく落とすよりも、まずは「体重の約5%減少」を一つの目安にする考え方があります。一般的な報告では、この程度の減量でも肝臓にたまった脂肪が減りやすくなり、肝機能の数値が改善する例が多いとされています。極端な食事制限ではなく、無理のないペースで数キロの減量を目指すことから始めると、続けやすいと感じる方も多いようです。例えば、70キロの人であれば、まずはおよそ3〜4キロ減らすことを目標にするイメージです。
体重が減ることで、インスリンの効きが改善し、血糖値や中性脂肪が安定しやすくなるといわれています。その結果として、肝臓への脂肪の供給が抑えられ、脂肪肝の改善につながる可能性があります。短期間で急激に体重を落とす方法は体への負担も大きくなりやすいため、日々の食事と運動を少しずつ見直しながら、現実的な減量幅を目指すことが重要です。夕食の量を少し抑える、間食や夜食を見直す、主食の量をほんの少し減らして具だくさんの味噌汁や野菜のおかずを増やすなど、小さな工夫の積み重ねが結果につながりやすくなります。
運動で脂肪が減りやすい背景
肝臓の脂肪を減らすうえで、運動は大きな味方になると考えられています。中強度からややきついと感じる程度の運動を、1日30分前後、週にトータルで数時間行うことで、肝臓にたまった脂肪が減りやすくなるという報告があります。早歩きの散歩や軽いジョギング、自転車こぎ、水泳など、自分に合った運動を選ぶと継続しやすくなります。まとまった時間がとりにくい場合は、10分×3回のように分けて行っても、トータルの運動量が増えれば意味があるとされています。
運動によって筋肉でのエネルギー消費が増えると、血液中の糖や脂質が利用されやすくなり、肝臓に余分な脂肪が送られにくくなるとされています。非アルコール性脂肪肝では、体重が大きく変わらなくても、運動だけで肝臓の脂肪が減るケースが報告されており、日常に少しずつ動く習慣を取り入れることが重要といえます。階段を使う、1駅分歩く、家事の合間にストレッチをするなど、特別な道具がなくてもできることはたくさんあります。体調や持病によって適した運動強度は変わるため、無理のない範囲から始めることが大切ですし、不安がある場合は主治医にどの程度の運動なら安全か相談してから始めると安心です。
果糖系甘味料を控える重要性
清涼飲料水や甘いジュースに多く含まれる果糖ブドウ糖液糖などの果糖系甘味料は、摂り過ぎに注意したい成分とされています。果糖は血糖値を急激に上げにくい一方で、主に肝臓で代謝されるといわれており、その過程で中性脂肪や尿酸が増えやすいという指摘があります。こうした背景から、果糖系甘味料を多く含む飲み物の多飲は、脂肪肝の悪化につながる可能性があると考えられています。喉の渇きを感じるたびに甘い飲み物を選ぶ習慣があると、知らないうちにかなりの糖質をとっていることも少なくありません。
日頃から甘い飲み物が習慣になっている場合は、水やお茶、無糖の炭酸水などに置き換えるだけでも、肝臓への負担を軽くできる可能性があります。いきなりすべてをやめるのが難しい場合は、1日の本数を減らす、薄めて飲む、サイズを小さくするなど、段階的に量を減らす工夫も一案です。成分表示を確認し、なるべく糖質量の少ない選択肢を意識することも、長い目で見て肝臓を守ることにつながります。甘いもの自体を完全に禁止するのではなく、「特別な日のお楽しみ」や「週に数回まで」など、自分なりのルールを決めて付き合うことが現実的です。
脂質の質を見直す考え方
脂肪肝というと「脂質はすべて控えるべき」と考えたくなりますが、実際には脂質の量だけでなく「質」に目を向けることも大切といわれています。バターや肉の脂、ココナッツオイルなどに多い飽和脂肪酸は、とり過ぎると中性脂肪やLDLコレステロールの増加につながりやすいとされています。一方、オリーブオイルやナッツ、青魚などに多い不飽和脂肪酸は、血中脂質のバランスを整えやすいとされることが多いです。日々の食事の中で「完全に脂質をゼロにする」のではなく、「どの油をどのくらい使うか」を意識することが重要です。
とくに、青魚やえごま油、アマニ油などに含まれるオメガ3脂肪酸は、非アルコール性脂肪肝の方で肝臓の脂肪や炎症が改善したという報告もあり、適量を意識したい栄養素の一つといえます。焼き魚や煮魚を週に数回取り入れる、刺身や缶詰をうまく活用するなど、無理のない範囲で取り入れられる方法を探してみると続けやすくなります。ただし、どの油であってもカロリーが高い点は変わらないため、使い過ぎには注意が必要です。揚げ物を減らして、蒸す・ゆでる・焼くといった調理法を増やすだけでも、総脂質量を抑えやすくなります。持病がある方や脂質制限が必要と言われている方は、自己判断をせず、主治医や管理栄養士と相談しながら調整してください。
コーヒーと緑茶の活用ポイント
日常的に飲まれているコーヒーや緑茶は、肝臓の健康をサポートする可能性がある飲み物としても注目されています。一般的な報告では、コーヒーを習慣的に飲んでいる人は肝機能が良好な傾向がある、脂肪肝や肝がんのリスクが下がる可能性があるといったデータが示されることがあります。これは、コーヒーに含まれるクロロゲン酸などのポリフェノールが、炎症や酸化ストレスを和らげる働きを持つためではないかと考えられています。ただし、砂糖やクリームをたっぷり加えるとカロリーが増え、せっかくのメリットが相殺されてしまう可能性があるため、なるべく無糖または控えめな甘さで楽しむことが勧められます。
一方、緑茶にもカテキンをはじめとしたポリフェノールが含まれており、非アルコール性脂肪肝の方で肝臓の脂肪や炎症が軽減したという報告があります。1日に何杯飲むかは体質やカフェイン感受性によって適量が変わるため、一般的には無理のない範囲で数杯程度を目安に考えるとよいとされています。カフェインのとり過ぎが心配な場合は、ノンカフェインや薄めのものを選ぶ方法もあります。胃が荒れやすい方や睡眠に影響が出やすい方は、夕方以降の量を控えるなど、自分の体調に合わせた飲み方を心がけてください。
肝臓に良い食品の上手な取り入れ方
肝臓をいたわる食事として、大豆製品、ごま、青魚、しじみ、野菜や海藻、きのこ類などがよく取り上げられます。大豆製品にはたんぱく質や大豆イソフラボンが含まれ、ごまにはセサミンと呼ばれる成分が含まれており、これらが肝臓の負担を和らげる可能性があるとされています。アボカドや緑黄色野菜には、抗酸化作用を持つ成分が多く含まれ、肝細胞を守る働きをサポートすると考えられています。普段の食卓で、味噌汁や冷奴、納豆、胡麻和え、野菜たっぷりの副菜を少しずつ増やすだけでも、肝臓にとってはプラスに働きやすくなります。
しじみのタウリンや、にんにく・玉ねぎに含まれる含硫アミノ酸、ビタミンDやマグネシウム、食物繊維なども、全身の代謝や解毒を支える要素として注目されています。ただし、特定の食品だけを大量にとれば良いというものではなく、主食・主菜・副菜を組み合わせたバランスの良い食事が基本とされています。塩分や脂質、アルコールなど、他の要素とのバランスも重要です。持病や服薬内容によっては、制限が必要な食品もあるため、気になる点がある場合は医療機関や管理栄養士など専門家に相談しながら調整することが大切です。日々の小さな選択の積み重ねが、数年先の肝臓の状態を大きく左右すると意識しておくと、食生活の見直しにも前向きに取り組みやすくなります。
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療・予防を意図するものではありません。健康状態や治療については人によって異なるため、症状がある方や投薬中の方は自己判断せず、必ず医療機関や専門家の指示に従ってください。
肝臓の脂肪を落とす方法に関するまとめ
・脂肪肝は自覚症状に乏しく検診と数値チェックで早期発見を心がける
・アルコールを飲まなくても糖質やカロリー過多で脂肪肝になる可能性を理解する
・脂肪肝が進行するとNASHや肝硬変など重い肝疾患に発展しうるリスクを意識する
・血液検査のASTALTγGTPとエコー検査で肝臓の状態を定期的に確認する習慣を持つ
・体重の約五パーセント減少を最初の目標に無理のないペースで減量に取り組む
・日常生活に早歩きや階段利用など中強度の運動を組み込み継続してエネルギー消費を増やす
・清涼飲料水や甘いジュースを減らし水やお茶など肝臓に負担の少ない飲み物を選ぶよう意識する
・脂質は量を減らすだけでなく飽和脂肪酸を控え不飽和脂肪酸を上手に取り入れる考え方を持つ
・青魚やえごま油などオメガ三脂肪酸を含む食品を食事に少しずつ取り入れていく工夫をする
・コーヒーや緑茶は砂糖やミルクを控えめにしつつ自分の体質に合う量で楽しむようにする
・大豆製品や野菜海藻きのこ類など肝臓を支える食材を毎日の食卓にコツコツ増やしていく
・特定の食品やサプリに頼り過ぎず主食主菜副菜をそろえた全体のバランスを重視して食べる
・持病や服薬がある場合は自己判断で食事や運動を変えず必ず医療専門職に相談して調整する
・数値の変化に一喜一憂し過ぎず半年一年といった中長期の視点で生活習慣を整える意識を持つ
・肝臓のケアは自分と家族の将来のためと考え無理のない範囲で今日からできることを一つ始める
健さんの視点コラム
肝臓の数値が気になり始めると、完璧な食事や急な運動で一気に変えようとして続かなくなる方を多く見てきました。昨日より一歩多く歩く、甘い飲み物を一本減らすなど、日々の小さな選択の積み重ねが、時間が経つほど確かな変化につながっていきます。
周りと比べて焦るより、自分のペースでできる一つの行動を静かに続けていくことが、未来の自分をそっと支える力になります。こうした歩みを大切にしながら、これからも自分にとっての人生健康第一を無理なく育てていきましょう。
健さんの他の記事:業務スーパー無添加食品を賢く選ぶための基礎知識
肝臓に脂肪がたまりやすい背景には、食事や運動だけでなく、日常の飲み物の習慣が影響していることがあります。とくにアルコールは摂取量に応じて、体が優先的に代謝しようとするため、他の脂質が後回しになり、脂肪が蓄積しやすくなると言われています。
毎日飲む方が急に完全にやめる必要はありませんが、肝臓を休ませる“余白の日”をつくるだけでも、脂肪の蓄積が緩やかになることがあります。最近は香りや味わいが本格的で、満足度の高いノンアル飲料が増えているため、負担を減らしたい日の置き換えとして取り入れやすくなっています。無理な我慢ではなく、楽しみながら肝臓への負担を減らす工夫の一つとして、ノンアルを試してみるのも自然な選択肢です。
楽天はこちら
アマゾンで探す
最後まで読んでくれてありがとうございます、応援クリックで励まされます!これからもよろしくお願いします。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d44b984.a2cedfef.4d44b985.a3dc184f/?me_id=1306273&item_id=10006198&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsoukaidrink%2Fcabinet%2F410%2F65410.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)